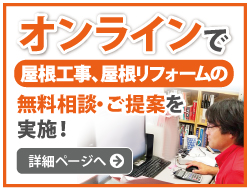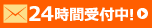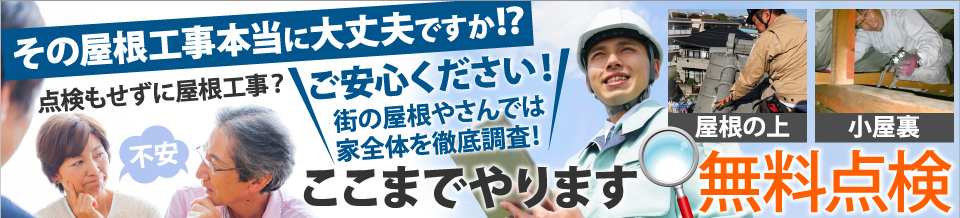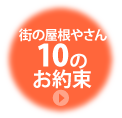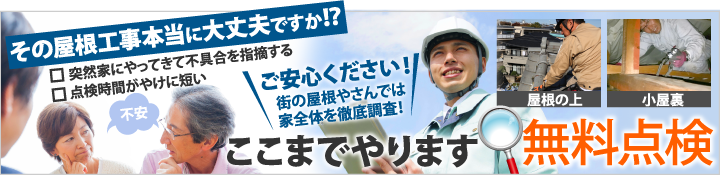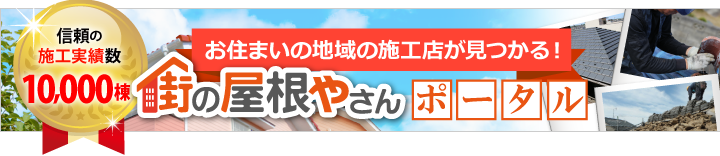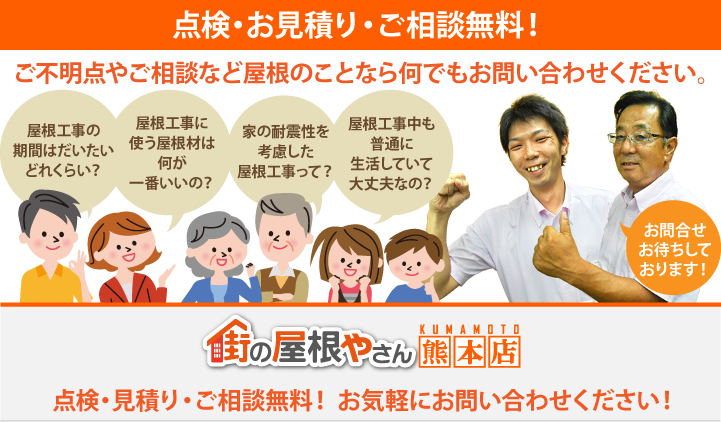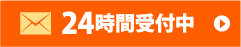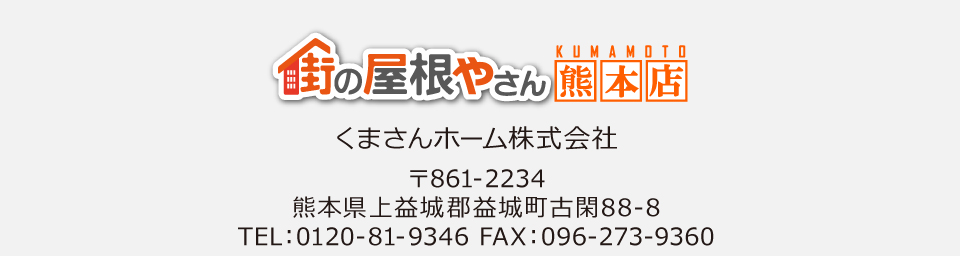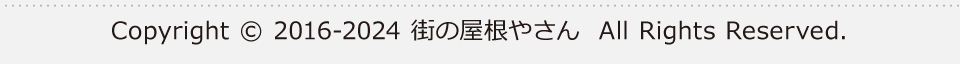熊本店発・この症状は『結露』『雨漏り』のどっち?|発生時期や場所によって見分けるポイントがあります。

外気と室内の温度差ができると、『窓の周りに水滴がついている』『天井が湿っている気がする』などのご経験はありませんか?
住まいで起こる水関係のトラブル『結露』と『雨漏り』は、一見すると症状はよく似ていますが中身は全く別物です。今回は見た目が分かりづらい『結露』と『雨漏り』の見分け方についてご紹介させていただきます。
※街の屋根やさん熊本店でも『結露』or『雨漏り』どちらなのか現地調査を行いました
▶菊池郡大津町で天井にできたシミは雨漏りか結露か調査しました
※街の屋根やさん熊本店でも『結露』or『雨漏り』どちらなのか現地調査を行いました
▶菊池郡大津町で天井にできたシミは雨漏りか結露か調査しました
1.『結露』と『雨漏り』とは?
 | 空気中の水分が冷やされる事で起こる現象。 身近な結露で言えば、冷たい物を注ぐとコップの外側が濡れてくる事です。 住まいでは、主に室内と外の温度差によって起ります。 |
 | 屋根・外壁の隙間から雨水が入り込み起こる症状。 住まいのどこかで不具合が起っている状態です。 |
2.『結露』or『雨漏り』見分け方のポイント

『結露
・発生する時期がいつか
・どこで発生するか(場所・範囲
お住まいで気になっている水濡れや湿り気
確認して見ましょう!
・発生する時期がいつか
・どこで発生するか(場所・範囲
お住まいで気になっている水濡れや湿り気
確認して見ましょう!
 | 秋~冬にかけての寒い時期・室内に暖房を入れた時・窓ガラスや壁一面など広範囲に発生する・換気を行うと改善する |
 | 季節は関係なく、台風や雨の日などに発生する・窓枠やサッシ、壁や天井の部分的に発生する・室内がカビ臭いなど建物内部にも影響が出る・換気を行っても状況は変わらない |
2-1 ポイントⅠ:『発生時期』

『結露』と『雨漏り』は、水濡れがどのタイミングで発生するかで大体は判別が可能です。
秋~冬にかけて寒い時期に水滴等が発生する場合は『結露』が考えられます。
暖房をよく使用し、換気が十分でなく湿気が溜まりやすい室内は発生しやすくなります。
反対に季節は関係なく雨の日等に水濡れが起こる場合は『雨漏り』の可能性が高くなります。
2-2 ポイントⅡ:場所・範囲

どの辺りでどの位水漏れが発生するのかも特定の目安となります。
壁・窓ガラスの表面・サッシ全体など広範囲に水濡れする場合は『結露』の可能性が高くなります。
窓ガラスの窓枠・サッシや壁の一部などの限定された範囲に水滴などが出てくる場合は、『雨漏り』を疑いましょう。
水濡れ箇所が換気しても乾かない時は、雨漏りの可能性が高いでしょう。
雨漏りは室内に症状が現れるまで、時間を掛けて建物内部に雨水が伝わり湿気がこもった状態が続きます。
『クロスの黒ずみ』『カビ臭い』が起れば雨漏りに間違いありません。
『クロスの黒ずみ』『カビ臭い』が起れば雨漏りに間違いありません。
3.『結露』『雨漏り』の対処法
3-1 結露だった場合の対処法

結露だった場合の対処法は『換気・除湿で湿気を減らす』『断熱をして冷たい空気を家の中に入れない』事です。
すぐにできる対処法では『換気』や『除湿』をする事で、室内の湿気を軽減させる方法です。
普段の生活で取り入れやすい対策をご紹介します。
窓ガラス一面に水滴が付いている場合は、結露かもしれません。
一度、上記の対策を試みてはいかかでしょうか。
3-2 結露防止グッズ
 | 『窓下・専用ヒーター』 | 窓の下に置き空気を温めて、窓ガラスにできる結露を抑制してくれます。また、トイレや机の下などの狭いスペースで、足元専用のヒーターとしても幅広く活用する事ができます。 |
 | 『結露防止・断熱シート』 | 断熱効果のあるシートで、窓やドア用のものがあり、手軽にご自身で貼る事が可能です。窓やサッシから伝わってくる冷気の軽減ができ、防寒対策にもなりますよ。 |
 | 『二重窓(内窓)』 | 内側にもう1枚窓を設置し二重構造にするリフォームです。 二重構造・窓の空間に空気層ができるので、冷気の侵入を防ぎ結露の防止になります。使用するガラスやサイズによって費用に違いがありますので、業者へ確認が必要です。 |
3-3 結露防止の工事方法

『屋根・断熱工事』
夏は日射熱の侵入を防ぎ、冬は熱を逃げにくく暖かい部屋を保つ事ができます。
外気からの急激な温度変化がなくなり、断熱する事で結露対策にもなります。
施工方法は、屋根裏(内側)に断熱材(グラスウールetc)を吹付ける方法と、屋根の改修に合わせて屋根の上側(外側)に断熱材を施工する方法があります。
▶屋根断熱のメリットと屋根リフォームで行うべき断熱対策
▶屋根断熱のメリットと屋根リフォームで行うべき断熱対策
4.雨漏りだった場合の対処法

雨漏りが発生した場合は、先ずは業者へ連絡をして現状をの調査依頼をお願いします。
①業者へ雨漏りの調査依頼➙②雨漏りの原因特定➙③雨漏りの修理の手順で雨漏りを直していきましょう!
①業者へ雨漏りの調査依頼➙②雨漏りの原因特定➙③雨漏りの修理の手順で雨漏りを直していきましょう!
室内に雨染みとなって現れるまでには構造内部を伝ってくる為、雨漏り箇所の特定は安易な物ではありません!
雨水の浸入口は一つとは限らないのです。
目視だけでは雨漏り箇所の特定ができなければ、お客様に説明の上、別途費用が必要な雨漏り調査を行う場合もあります。
▶雨漏り修理・雨漏り改修工事は街の屋根やさんへ
▶確実な漏水箇所の特定のための散水検査
4-1 雨漏りの調査方法(※別途費用が必要です)
| 調査方法 | 詳細 |
| 『目視調査』 | 目で見て現状を確認する方法です。 屋根のズレや歪み,外壁のひび割れなど、目で確認できる範囲内で行います。 |
| 『散水調査』 | 雨漏りが疑わしい箇所にホースで水を撒いて、室内に漏水が発生するのかを確認します。 雨や暴風雨と同じ状況を作る事によって、雨漏り箇所の特定が可能です。 ※調査時に使用する水道につきましては、お客様宅の水道をお借りします。 |
| 『発光液調査』 | 紫外線(ブラックライト)を当てると光る塗料を水に混ぜて、雨漏りの原因になりそうな箇所に流す調査です。 浸透した箇所に様々な色に変えて見せる事で、侵入経路を突き止める事ができます。 |
| 『赤外線・サーモグラフィー調査』 | 赤外線を検知するカメラを使用し、建物の温度を測定する調査です。 水が浸透している箇所は温度が低く、水の浸透が鳴り箇所は反対に高くなり、温度の違いによって雨漏り箇所を見つけ出す事ができるのです。 |
5.雨漏りが発生した建物の被害事例
5-1 事例①:屋根下地材の腐食



5-2 事例②:棟瓦のズレ



5-3 事例③:棟板金の浮き(釘抜け)



5-4 事例④:漆喰の劣化



6.まとめ

今回は『結露
『結露
★時期=いつ発生するのか
★場所・範囲=どこで発生するか
こちらの2つのポイントで、チェックしてみて下さい。
結露や雨漏りは正しい対策と予防が必要です。
快適に暮し、住まいを”水”から守り為にも、日頃から小まめに点検やメンテナンスを行いましょう!
街の屋根やさん熊本店は、そんな点検のお手伝いをさせて頂きますので、お気軽にご相談下さいませ♪
▶メールでのお問合せ(24時間受付中)
『結露
★時期=いつ発生するのか
★場所・範囲=どこで発生するか
こちらの2つのポイントで、チェックしてみて下さい。
結露や雨漏りは正しい対策と予防が必要です。
快適に暮し、住まいを”水”から守り為にも、日頃から小まめに点検やメンテナンスを行いましょう!
街の屋根やさん熊本店は、そんな点検のお手伝いをさせて頂きますので、お気軽にご相談下さいませ♪
▶メールでのお問合せ(24時間受付中)